社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
半世紀以上前に卒業した県内の高校の同窓会から、年1回発行の会報が届いた。学校創立130周年ということで、かなり力が入っている。まずは、県教育委員会からの県立高校共学化の方針に異議を唱えている。
創立以来男子校だった母校で培われた教育成果を重視し、その伝統を守ろうというのだ。私の記憶では、入学早々の10キロマラソン、夏の臨海学校での遠泳、秋の50km超の古河マラソンなど伝統的体育行事が目白押しで、いささか辟易したものだ。その頃の空気がまだ残っていることに懐かしさより驚きがあり、別学維持のために浦和でデモまで実行したことには、アナクロとさえ感じた。
終戦後の1948年4月より新制高校がスタートしたが、前年に文部省が出した文書では、共学の実施より男女の機会均等の重視と地方の実情・要望の尊重が優先されていた。『男女共学の成立』(2021年刊 六花出版)の編者、京都大学名誉教授・小山静子氏が「関西に住んでいると、国公立の高校は共学が当たり前であり、男女別学は私立の学校のみにある、もっと言えば私立の進学校の話だと思われている節もある」と述べているように、関東とはかなり様相が違う。別学校が多いのは群馬、栃木、埼玉の各県だ。
地域による違いは、戦後のGHQの地方軍政部における対応に差があったからだ。関西のほうが軍政部の指導が強かったという。
そして小山氏は「性別というものが絶対的な差異だと考えられていた時代ならともかく、性の自明性が疑われている現代において、何を根拠に別学校が存在しうるのかと思ったりもする」と述懐した上で、「共学と別学の問題は複雑であり、何とも微妙な割り切れなさを感じてしまうし、多くの人が自らの経験というものに妙にとらわれていると気付く」と指摘している。自らの経験を主な論拠とする別学派の人たちはそれに当てはまるかもしれない。
山田洋
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR

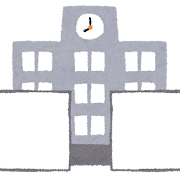
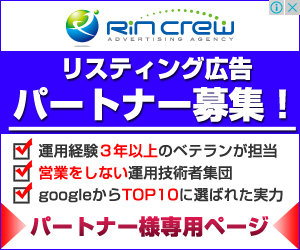

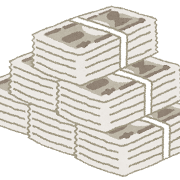
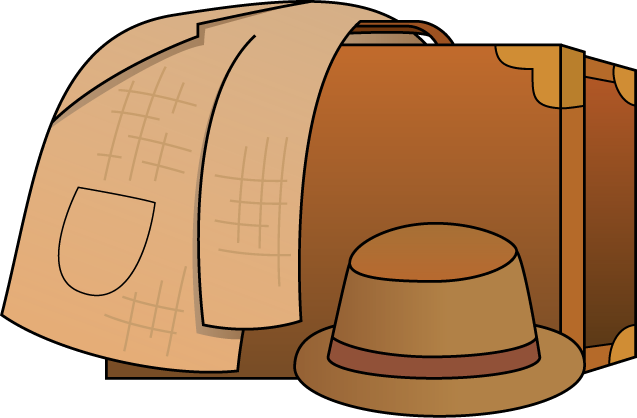
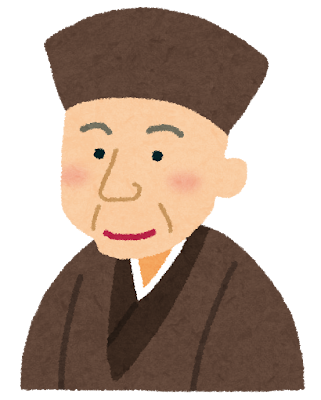

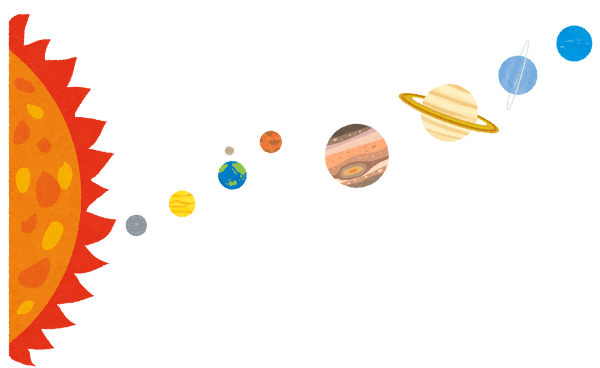




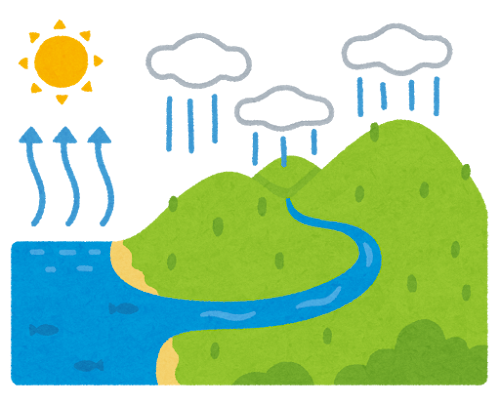
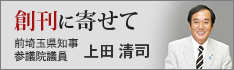
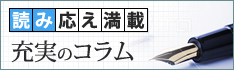

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

