社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
東京・蒲田の神社で宮司をやっている旧友が「お祭りなのに露天が3軒しか出なかった。来年は真剣に対策を考えなければ」と頭を抱えていたら、千葉に住む仲間も「以前は町の祭りに出かけていたけど、何年も前から行かなくなったなあ」と相づちを打っていた。私の地元のさいたま市中央区では、本町通りを中心にした「与野夏祭り」が7月に開催され、相変わらず来訪客でにぎわっていたが、露店商の数は2~3年前より減っていた。
松竹映画『男はつらいよ』シリーズは的屋(テキヤ)と呼ばれた露天商の寅さんが毎回引き起こす騒動で日本中を笑わせたが、寅さんがお客相手に繰り出すテンポのいい口上に喝采する人も多かった。長い歴史を持ち、寺や神社の縁日に独自の役割を担ってきた的屋・露天商が減った理由はいろいろ考えられる。
人手不足ということもあり、この職業を選ぶ人が減ったのは確かだ。毎日がお祭りや縁日というわけではないので、年収も多いとは言えない。兼業は当然で、家族やアルバイトの助けに頼ることも多い。寅さんのようなプロフェッショナルは今や絶滅危機に瀕しているのかもしれない。
露天商の数は減っても、お祭りが存続しているならばまだよい。私の実家がある農村は2010年に久喜市に合併されたが、数年前から地域の祭りそのものが実施されなくなった。情報交換の場でもあった祭りが消滅したことで、地域の情報が途絶え、田舎独得の厚いコミュニケーションも薄くなる一方だという。
ますます味気ない世の中になってしまいそうだが、行政としても少しは策を考えてしかるべきだろう。
山田洋
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR

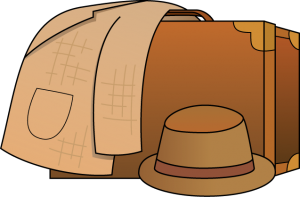
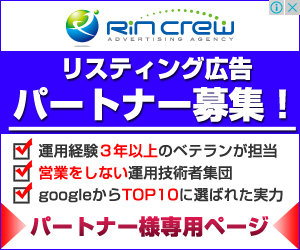




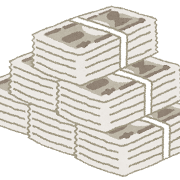
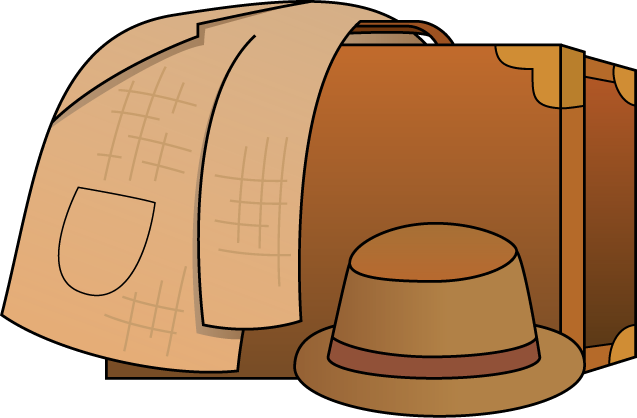
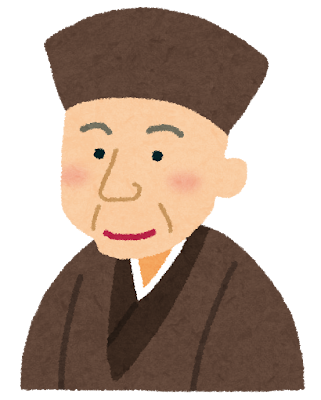

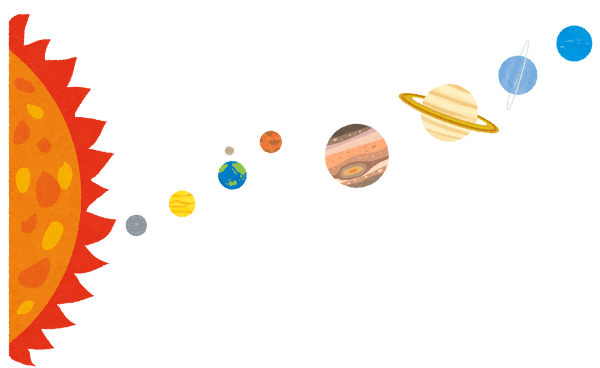


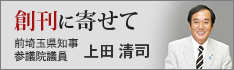
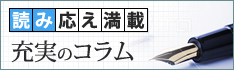

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

