社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
紀州のドン・ファンと呼ばれた艶福家の野崎幸助さん(享年77歳)が自宅で謎の死をとげてから2か月が過ぎようとしている。遺体から覚醒剤の成分が検出され、今年2月に結婚したばかりの55歳年下の再々婚相手に疑いの目が向けられているが、決定的な証拠は出てきていないようだ。
若い(特に20代の)女性を口説きまくり、著書『紀州のドン・ファン 美女4000人に30億円貢いだ男』(講談社+α文庫)等でも女性への派手な金遣いを明かしていたので、悪い奴に狙われるのではと危惧していたが、事態はその方向に進んでしまった。
でも、「まだ男性器は健在」、「女体こそが人生」と言い放っていた野崎さんの女性遍歴に驚き、羨望を感じた高齢男性は少なくなかったようだ。お相手となった4000人の女性については、即物的な表現ながら明るく回想している。小柄で学歴も中学卒の彼がこんなに多くの女性を口説き落とせたのは、人柄もあろうが、やはりお金をケチらず奮発し続けたからだろう。
野崎さんの女性談義を読んで、彼と同年齢の裕福な主人公が最後のあがきのような性行動をとる小説を思い出した。谷崎潤一郎の『瘋癲(ふうてん)老人日記』である。1961年から翌年にかけて雑誌「中央公論」に連載された作品で、作者も75歳になっていた。
主人公の卯木督助はまったく性的不能に陥り、高血圧や神経痛を抱えているが、好色本能は衰えていない。東京狸穴の邸宅には老妻、息子夫婦と孫、住み込みの看護婦、家政婦2人がいる。督助は今は働いていないが、かなりの資産家で、教養もあり、趣味も豊かだ。そんな彼が息子の嫁、颯子の肉体、特にその足に強くひかれていく。
彼女は浅草近辺の生まれの元ダンサーで、留守がちな夫との仲は冷えきっている。性的に興奮することは危険と知りながらも、督助の颯子への執着は増す一方だ。そしてついに彼女の足をしゃぶることを許され、死への恐怖と興奮と快感が代わる代わる胸を突き上げる。嗜虐的で娼婦性のある彼女に対する督助の行動の裏には母親への甘えに共通するものがあるようだ。彼女のほうも老人の要望に応じつつ、宝石など高価な贈り物をねだるが、彼は嬉々として受け入れる。
死を意識するようになった督助は京都の法然院を墓地と決め、墓石に颯子の足裏の形を刻み、その足裏の下に自分の骨を埋めることにする。こんな調子で日記の形をとった物語は自虐的かつ戯画的で、徹底してユーモラスで、病的な臭いはしない。
颯子のモデルは、谷崎の義妹の息子の嫁だとされる。この人は谷崎に足型をとられ、言われるままに彼を踏みつけたことがあったという。谷崎はマゾヒストで足へのフェティシズムは生涯一貫していた。
若い頃に変態性欲を書いていた谷崎は『細雪』で純日本的な世界に戻ってきたとされた。実は、1942年の執筆開始当時は日本美の世界よりも変態性欲みなぎるものを書きたかったのだが、「中央公論」で連載されるや、警察や軍から注意を受け、連載も打ち切られた。発表の場もなく書き続けたものの、押収されるのを恐れ、おとなしい内容になった。戦後の1948年に完結すると、谷崎の代表作のような扱いを受け、翌年には文化勲章を授与され、1960年代にはノーベル文学賞候補にまでなった。
そんな谷崎が晩年にこの作品を書き上げたのには喝采したい。平仮名を使わず、片仮名と漢字の日記は最初は読みにくいが、次第に督助と作者が二重写しになり、笑いが止まらない面白さだ
山田 洋







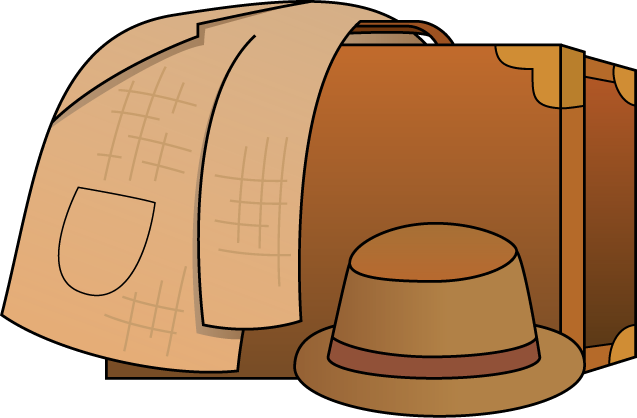
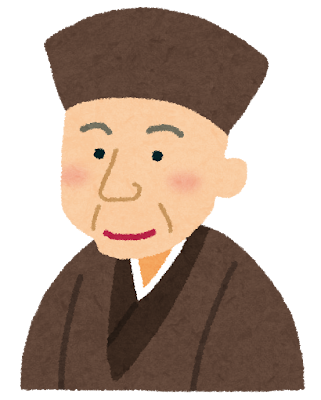

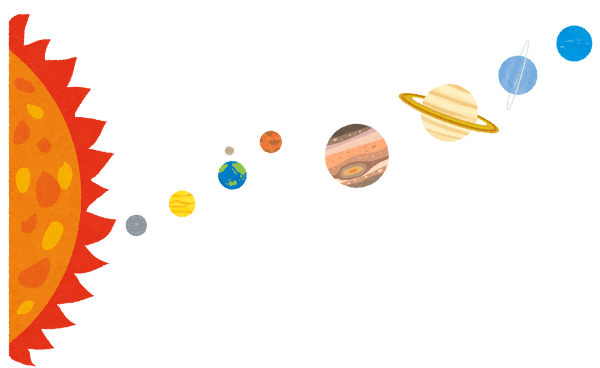






![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

