トップページ ≫ なでしこ便
なでしこ便
女性ならでは眼コミ、口コミ、スパイシー語録
-
- 全ては断捨離から始まる(2024年12月17日)
-
いらないものを置いている場所こそ死んだ場所。デッドスペースというが、断捨離により、スペースに新しい気が宿ると、良いことが起きると言われている。物理的に時間やスペースの余裕ができることもあるが、断捨離は古代インドのヨーガによる悟りへの思想。 想いを断ち、捨て、執着を手離す。「断行・捨行・離行」から引用した言葉だ。 あるひとは、30年ぶりに畳をかえたら、…
-
- 姉の存在(2024年12月04日)
-
母が他界してから、毎朝くる姉からの電話。「元気?」「変わりない?」と毎日交わすたわいない会話。もう18年も続いている。お互いの日常を30分くらい話して、「また明日ね」と電話をきる。今では生活の一部。姉の声を聞かないと一日が始まらない。 先月、父が亡くなった。父と同居し、ここ数年は父の介護に明け暮れた姉。父のいなくなった空間を埋めるのにはまだまだ時間がか…
-
- 老舗の努力(2024年11月22日)
-
100年以上前からあるウナギ屋へ懐かしい友人4人と行ってきた。実家が近い子は常連だが、私を含めみな初めて訪れた店。常連の友達によると、10時過ぎから整理券を出すという。それほどの人気店なら並んででも食べたいのだなぁと感心していると、整理券を入手後、並ばなくて良いという。登録され、現在状況をラインで知れるシステム。観光地の中にある店なので、時間ぎりぎりまで散策…
-
- 秋刀魚苦いかしょっぱいか(2024年11月08日)
-
今年は秋刀魚が安くて美味い!近年秋の味覚&庶民の味方サンマが高くて食卓から消えていた。どうやら気候変動などで何時もの漁場で捕れにくくなっていたようだ。はらわたごと食べるのが好きで、毎年酒のアテに楽しみだったのだが、しばらくはホヤで我慢していた。子どもたちにも腸ごと食べさせようと、そのまま焼いたが、この苦みは受け入れられなかった。一緒に飲めるようになったら再度…
-
- ハロウィンの源(2024年10月31日)
-
大きなカボチャとサツマイモを頂いたので玉ねぎと煮てミキサーにかけてポタージュスープに。秋の味覚。これで気分はハロウィンだ。そもそもハロウィンはケルト民族の魔除けとしてカブを用いていた。しかしアメリカでハロウィンの時期にカブの生産が少なく、カボチャ置き換えられて広まったそう。この時期、カブもカボチャも美味しいので、魔除けとともに温かい煮物で風邪除けを!…
-
- ピンピンコロリを目指そう(2024年10月20日)
-
学生時代の友人のお父さんが亡くなった。94歳だった。前日まで自分で食事をつくり、翌日の朝、畑で倒れて亡くなった。まさにピンピンコロリ。沢山の孫やひ孫に見送られ、本当に幸せな人生だったと友人は話してくれた。 誰だって、寝たきりなんてなりたくないし、周りの人に迷惑なんてかけたくない。今日から少しだけ自分なりの努力をしてみよう。身体を作る食事と運動。日々の努…
-
- 醤油で秋を感じる(2024年10月02日)
-
地元にある弓削田醤油さんの高級なお醤油を買ってみた。 早速お刺身で試してみたら、美味いのなんの。 飲みたくなる醤油。そう感じたのは初めてだった。 保存料の入っていない生醤油。常温保存ができない。 普段はずぼらな私だが、必ず冷蔵庫に入れるようになった。 出始めた新米も美味しいし、さんまやキノコなど、この繊細なお醤油で儚い秋を堪能したい。…
-
- 初めてのリサイクルショップ(2024年09月16日)
-
着なくなった洋服を捨てるのは勿体ないので、初めてリサイクルショップに古着を持ち込んだ。スーツやセーターなど全部で15点。自分ではそこそこ良いものだから、2000円位にはなるのかと思っていた。だが引き取り金額はなんと715円。何年か前に買った高めのスーツは1円だった。女性の洋服は流行に大きく左右されるため、引き取り金額はかなり厳しい。捨てるよりもいいのかと思い…
-
- 物価上昇をポジティブにとらえる(2024年08月29日)
-
沢山は食べられないお年ごろとなり、量より質に移行している。1回の食事を大切に無駄なく体にもいいものをと、一石三鳥も四鳥も欲張ってしまう。片付けが要らない外食は魅力的だが、金に糸目をつけないわけにもいかない。やはり好きなものを好きな量食べられる自炊は欠かせない。物価が上がり、どれをとっても安くはないので、少ない量でも美味しい食材を求めるようになった。ファステ…
-
- キュウリの馬とナスの牛(2024年08月16日)
-
今年もお盆がやってきた。 実家に帰ると8歳の孫がキュウリの馬をつくって待っていた。割りばしの足にトウモロコシの髭のしっぽ。小さな布で布団もつけてくれていた。盆迎えの帰り道は、曾おじいちゃんが落ちないようにと慎重にキュウリの馬を持っている姿が逞しく、嬉しかった。帰りはゆっくり帰れるようにナスの牛もつくっていた。ご先祖様を思う気持ち。これからも持ち続けて成…
新着ニュース
特別企画PR

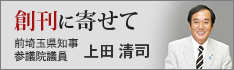
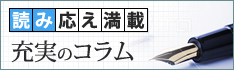

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

