社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
2、3週前の『サンデー毎日』で「週刊誌よ、今こそ牙を磨け!」と檄を飛ばしていたのは講談社『週刊現代』の元編集長・元木昌彦氏。彼が編集長だった1995年には発行部数150万部という記録を打ち立て、退職後も各種メディアにて発信を続けている。
元木氏はまず、古巣の『週刊現代』を槍玉に上げる。毎号、相続問題と高齢者の病気を特集して、老人雑誌と見紛うほどに変貌し、さらに今春からは合併号を出すという形で、実質的に月3回発行となってしまった。先頃、掲載した韓国特集が嫌韓をあおるとして批判された小学館『週刊ポスト』も、同じような編集内容に傾斜しており、両誌とも週刊誌である必要がなくなる日が近いのではと嘆く。
1960年代末に講談社に入社した私は『週刊現代』編集部に配属され、数年後に元木氏が月刊誌編集部から異動してきた。当時は新聞社系週刊誌に代わって出版社系週刊誌の隆盛期で、編集部は活気に満ちていた。スキャンダリズムと、記者クラブに所属しない故のゲリラ取材が持ち味で、それを担った契約記者の存在に元木氏は着目する。彼らの多くは大学で学生運動に加わり、退学処分になったり、自主退学をしていた。当然、血気さかんで権力を嫌い、強者におもねることを否定していた。
そのような記者たちの中から多数の人材が輩出された。6年半在籍した私のところにも有能な人が加わってくれた。最初が宮崎学氏。後にグリコ・森永事件のキツネ目の男と同一人物かと疑われたこともあったが、自伝的な『突破者』で注目され、アウトローの世界などを書き続けてきた人だ。次がまだ少年の面影が残っていた笠井潔氏だ。原稿の文字がきれいだったのは印象的だったが、小説家として活躍することになるとは想像できなかった。そして私より3つ年上の上野昂志氏。当時から漫画や映画の評論で知られていたが、中国の魯迅の研究者でもあった。温厚な人で、どんな取材でも引き受けてくれた。このような人たちと一緒に仕事をしたことの意義を感じたのはずっと後のことだった。
時代が変わり、週刊誌を作る人たちの気風も変わり、個人情報保護法の成立とか名誉毀損の賠償額の高額化など週刊誌への逆風が吹き続けた。それでも『週刊文春』のようにスキャンダリズムを維持しているところがあるのは救いだ。ただ、元木氏は「芸能人や小物政治家のものばかりで、政権を揺るがすスキャンダルにはお目にかかれない」と手厳しい。
机を並べていた頃にも増して反骨ぶりを披露する彼の提言には、スキャンダリズムとは縁遠かった私でも共感する点が多い。彼のライバルでもあった他社の週刊誌編集長が、今や右派系雑誌で露骨な権力擦り寄り路線をとっているのを見ればなおさらだ。
山田 洋






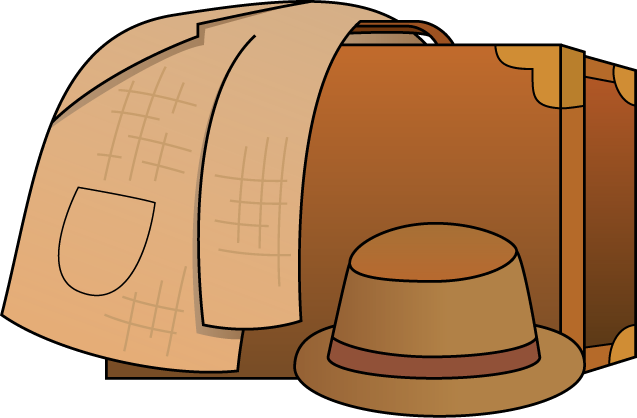
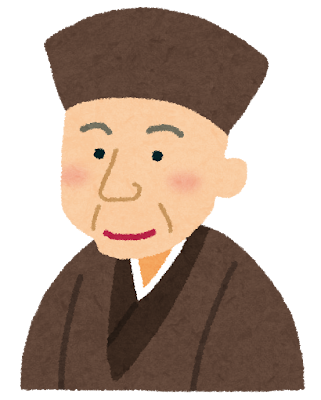

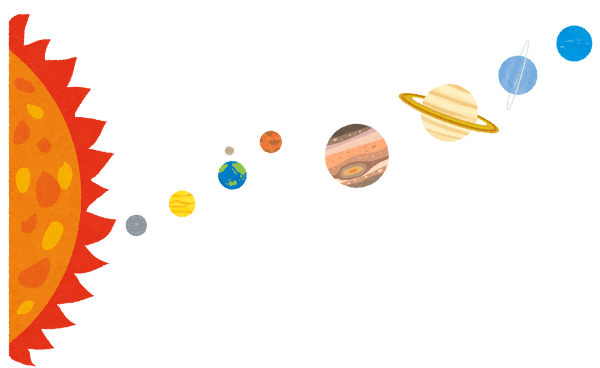







![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

