トップページ ≫ コラム ≫ 男の珈琲タイム ≫ 地方の帝王 ―市長の事情― part3(2)
コラム …男の珈琲タイム
マッカーサーは敵の大将だ。その大将に私の父は尊敬の念をもって視線をむけた。マッカーサーは、私に近づいた。魔王のような太い大きな手が私の頭におかれた。そして、撫でた。私は、その大きな格好の良い男を見上げた。「ユーアー、グッドボーイ」。私は形容しがたい嬉しさでいっぱいになった。「サーキュー、サアー、ゼネラル」父は感動して、マッカーサーに深々と頭を下げた。マッカーサーは悠然と去って行った。私が「男」を感じた原体験かもしれなかった。
帰り、銀座のコーヒーショップに寄った。将校のS氏、両親と私の4人。「アナタハ キット エラク ナリマスヨ ダグラス・マッカーサー ニ アタマヲ ナデラレタノ デスカラ」S氏の言葉は私の人生の玉手箱だったし、マッカーサーの手の感触は生涯忘れがたい宝物となった。「コーヒー ドウゾ」とS氏。「コーヒー?」私は、両親の顔をうかがった。「そう、大丈夫よ、一郎。これがコーヒーなのよ。日本でいえばお茶よ」母が諭すように言った。「へぇ~、コーヒーか」私はおそるおそる、その異物のような外国のお茶に舌を入れた。瞬間、私は外国人になった。英語がペラペラ話せるような錯覚に陥った。美味しいというより、何かもう一つの世界に入っていけるような魔法の媚薬のように私は思った。それは、私にとってはお茶とはまったく違う舌感であり、珍味といってよかった。
(つづく)
(鹿島 修太)




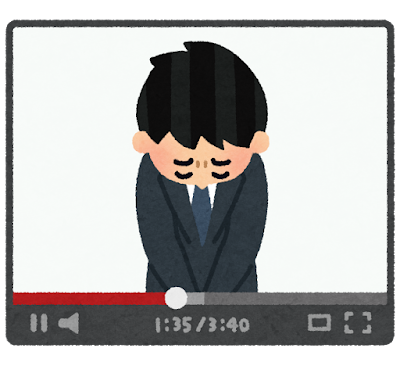


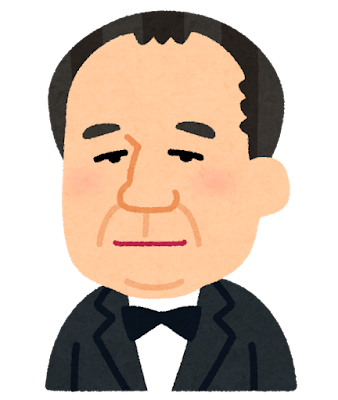








![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

