トップページ ≫ 文芸広場 ≫ 県政の深海魚(21)「ゴルフ場汚染」
文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
実力者だった牧田は県政を退いた。
そして地元の市長に就任した。牧田にとって市長職は決して名誉の座ではなかった。
県政という大海に比べれば小さな池のように思えた。牧田から輝きは失せていった。
六十の半ばで牧田は急激に老いた。夕陽を背に立ちすくむ老人のような寂寞たる孤影が、生まれ故郷の晩秋の中にぽつねんとあった。
そして次の市長選で敗れ、翌年死んだ。
あとを追うように岩木も亡くなった。誰も騒ぐことはなかった。
千曲は葬儀だけはまめに参列した。
他者の死は、千曲の生の証しでもあった。
線香の向こうの写真に手を合わせながら、千曲は一心に念じ続ける。祈ることと念じることが一体となって湧き水のような野望に変じていった・・・。
S県のゴルフ場は急ピッチで開発された。開発業者にとって関門は二つだ。
鏡知事部局と保守党実力者達だ。
この関所さえ通り抜ければ後はさして苦労はない。
「先生、この会員券は三千万ですが、すぐ五千万になります。勿論、先生には一銭も頂くことはできません。どうか、この会員券をお受け取り下さい。帳簿上には完璧にしておきます」
開発業者は多額の利益を得た。一方で実力者達の利益も莫大なものとなった。
そんな時、鏡知事の幹部がゴルフ場汚職で逮捕された。保守党幹部は慌てた。
しかし逮捕された幹部は決して口を割らなかった。
警察はジダンダを踏んで悔しがった。
〝敵は本能寺だ〟 捜査当局の暗黙の合言葉だった。
事件の真相は闇の中に葬られた。
その後もゴルフ場は次々に開発された。五ヶ所も六ヶ所も会員券を手に入れることが実力者の証しにもなった。
海はますます不穏な底知れぬ深海となっていった。
新聞記者、最上礼子は記者を忘れてしまっている。
(探偵になってしまったわ。私・・・)
苦笑しながら、いつのまにか我を忘れている自分を確認した。むしろ、礼子はさわやかな心になりきっていた。
「これだけスキャンダラスな事ばかり起こって、それでいて深海の中は見えないなんて・・・嫌だわ。私・・・許せない!千曲は完全に覇王気分だわ」
この数年、礼子は春彦を追い続け、そして春彦の完全な同志となっていた。
礼子の情報は確かで、春彦にとって大きな財産となっていた。
「本当にありがたい。しかし、君はあくまで毎朝新聞の記者なんだよ。それを忘れちゃ駄目だよ」
春彦はその都度礼子をたしなめた。
しかし、そういう自分にくすぐったい程の矛盾を感じていた。
「最上さんね、少しきつい言い方だけど、記者は天下を狙えないんだよ。記者はね、陋巷 に死すべきなんだよ。極端に言うとさ・・・」
「えっ陋巷って?」
礼子は率直に聞いてきた。
「陋巷ってさ、まあ、汚くて狭い所だよ。これが記者魂であり、記者の宿命のようなもんじゃない」
「あのね、わかってないんじゃないですか、信濃さん。私はとっくに記者を捨てています。信濃さんって意外と鈍いのね」
「記者を捨ててる?」
「そうよ。もう三年近くもこの世界にどっぷり浸かっちゃって。しかも信濃さんの考えてることが手に取るように分かっちゃうと、もうそれって、私の考えになっちゃって・・・ううん・・・考えじゃない、思想と言った方がいいわね。だから、もう記者なんて首になったって平気よ。それより、信濃さんの傍にいて色んな力になってあげたいの。ああ・・・言っちゃった・・・生意気ね、私って・・・」
春彦の好きなジャズが流れていた。
「ジャズ、アンド、フリーダム、ゴーハンドインハンドか・・・」
指で包んでいる水割りの氷が心地よく溶けていく。淡いアメ色のウイスキーとジャズが一体となって春彦と礼子を甘く酔わせていた。
「この流れているジャズもさ、自由への渇望の曲なんだね。この物悲しい音色は、実は鋼のように強い希望への歌だと思っているんだよ。素敵だね、ジャズってやつは・・・」
春彦は右手のグラスを二、三回静かに回した。
横に座っている礼子も同じような仕草をした。
目と目が自然に合った。
礼子は恥じらいの色を見せながら微笑んでいる。
男と女の強い電流のようなものが流れて、二人をセンチメンタルな世界へと誘った。
「いよいよ明日なんだ」
春彦は保守党分裂決起の日をこの世界で礼子にだけは伝えておこうと思った。
「分かってます!最後まで味方でいますから。あなたの・・・」
(つづく)
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR






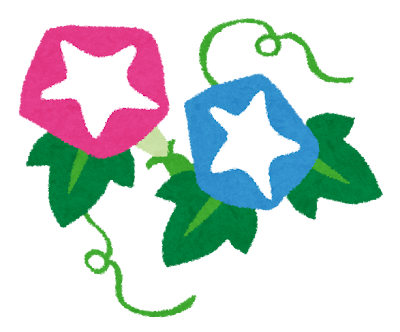



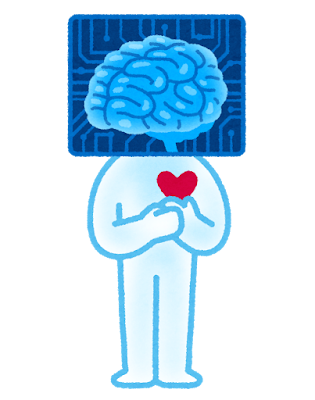
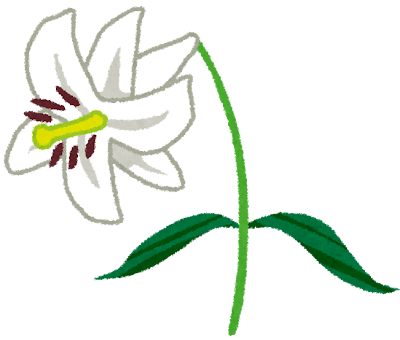




![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

