トップページ ≫ 文芸広場 ≫ 県政の深海魚(8)「汚れた市長選‐大量の逮捕者・後編」
文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
瀟洒な風呂敷包みがおもむろに置かれた。高さは二十センチ程あった。
西南総業のナンバーツーの朝比奈、ナンバースリーの保津、そして富士だ。朝比奈が口を切った。
「これは、オーナーの古川からの指示です。弊社のコンピューターで調べたところ、今度の市長選は信濃先生の勝ちです。どうか今後とも深くご指導頂きたく、お収め下さい」
朝比奈は深々と頭を下げた。下げながらも、そこには無言の圧力のようなものが漂っていた。
(西南総業の社員はH市だけでも二千人を越えるんだぞ。それに家族を入れたらもっと凄くなるんだ) 営業で鍛え上げてきた男ならではのオーラのようなものだ。
―― なるほど。今まで西南総業はこんな風にして市長の西川とつながってきたのか・・・
春彦は小説のような光景に出くわして、驚嘆した。
―― 俺も舐められたものだ・・・
春彦の矜持に怒りにも似たような感情が突きささった。
「私も人間です。空気だけを吸って生きている訳ではありません。しかし、この訳の分からない金を受け取ったら、その瞬間から私は御社の手先的な政治家になってしまうではありませんか。申し訳ないです。死んでも受け取ることはできません。お帰りになられたらオーナーの古川社長に申して下さい。信濃は青臭い若造でどうにも喰えない奴だ、と」
―― これで西南総業の票は大半西川にいくな・・・。
呟きながら春彦は内心ほくそ笑んだ。
―― これが俺自身の生き筋だ・・・一票差でも自力で勝ち抜くんだ・・・。
西南総業の幹部達は舌を巻いた。
「聞きしに勝る堅物野郎だ。こんな野郎は今までの政治家で初めてだ。恥をかかせやがって・・・見てろ!」
彼等の屈辱感は怒りに変わった。そして怒髪が天を衝いた。
その夜。西南総業は現役の西川支持の指令を社員達に下した。西南一家の指令は電光の如く各社員に響き渡った。
五百票差。
春彦の敗北が決まった。
「こんなふざけた選挙があるか」
開票場に集まってきた市民が口々に叫んだ。
当選が決定した翌日。
二人の刑事が春彦の自宅に飛び込んできた。
「信濃さん、小田の彼女の店を知ってますよね、とにかく教えて下さい」
哀願に近かった。
「刑事さん、どうしたんです?」
「いやいや、酷すぎる選挙違反でね。小田の女さえ見つかれば、全てが解決するんでね」
刑事の眼光に一瞬戸惑いながら、春彦は言った。
「そんな女のことまで知りませんよ・・・」
「嘘だ!信濃さんは知っている筈だ。今更、何で敵をかばうんですか。そんなきれい事で、政治なんて決して良くはならないですよ」
刑事の言葉は春彦への叱咤に近かった。ある意味で学校の教師の言葉にも聞こえた。
しかし、春彦は答えなかった。
―― 敗軍の将は兵を語らず・・・。
そんな気持ちの延長線に春彦の想いはあった。
三日が過ぎた。
早朝五時頃、悲鳴のように電話が鳴った。
「小田をはじめ、七人の市議会議員が逮捕されます。夕方です!」
毎夕新聞の川辺からだった。川辺は終始この市長選を追っていた。
「西川はこの選挙で三億を使ったそうですよ。捜査当局も驚いてます」
まるで勝ち誇ったようなジャーナリストの声に、春彦も衝撃を受けた。
夕方、七人の市議会議員が逮捕された。
百人近くの市民が事情聴取を受けた。
全ての新聞が全国版で報じた。
「信濃さん、次は市長の西川、県議の石沢もやると県警は言ってますよ」
川辺の電話は伝えた。
このあまりにも悪質な事件に県警は一気に勝負を賭けようとした。
しかし、裏で政治が動いた。
第一線の刑事達と担当幹部は歯軋りをした。
一方、市長の西川と県議の石沢は胸を撫で下ろしていた。
「H市の西川市長さんと石沢県議さんがお越しです」
国務大臣、谷山の秘書が告げた。
当選六期の谷山はH市を基盤の一つとしていた。
市長の西川は、この谷山には全く頭が上がらなかった。まして、選挙違反を救ってくれた恩はさらに西川の地位の低下を著しくした。
「やあ、やあ、お疲れさん。大変だったですなぁ。でもよかった。私の力が少しはお役に立てて。ハハハッ・・・」
谷山は応接用の椅子に深々と座って、いかにも恩着せがましく言った。
「本当の事を言うとね、当局を抑えるには、かなりの神経を使いましてね。あまりに圧力的になっちゃいけないし、まあ・・・その辺はうまくやって・・・まあ・・・上手くいきましたな」
谷山は自分の権力の強さを誇示するように、ぐっと西川と石沢を睨んだ。そして、急に微笑に似た笑顔を作った。谷山はポーズを幾通りも用意しておいて、時と場に応じて自らを自由自在に変貌させるテクニックを持ち合わせていた。
「この度は本当に助かりました。命が縮む思いでしたよ。このご恩は生涯忘れません。本当にありがとうございました」
まず、市長の西川が頭を下げた。平身低頭を絵に描いたような礼容を見つめながら、谷山はいかにも満足げに言った。
「まあ、まあ、いいから、いいから。逃れることができただけでもうこれ以上のことはないんだから」
谷山はいかにも忘れていたかのように、腕時計を見た。
「どうですか、じゃ、例の場所で?」
谷山が促した。
大臣室から車で十分のところに、その料亭はあった。
市長の西川がおもむろに分厚い風呂敷包みを差し出した。
「あ、あ、これは、これは・・・」
都会はいつも暮れ泥む街だ。しかし陽は必ず傾いていく。そして、沈む。火色に媚茶がかかった残映を留め、落日は愁絶の塊となって朽ちていった。
(つづく)
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR






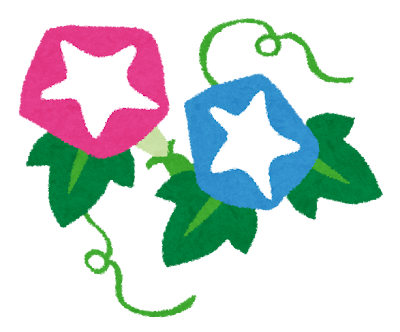



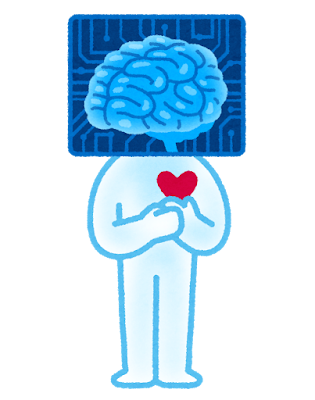
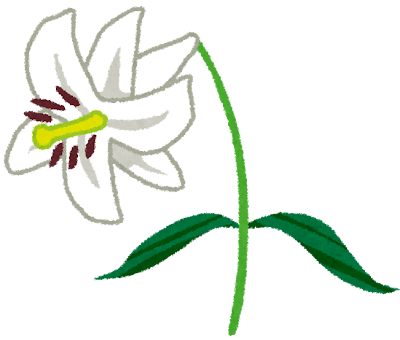




![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

