社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
75年前の1941(昭和16)年12月8日に日本は米英両国との戦争に突入し、ハワイ真珠湾を空襲した。今から見れば、戦力や国力で勝ち目のない相手に戦いを挑んだのは理解しがたい。為政者の責任は重大だが、彼らがそのような道を選んだ背景には国民の感情や意識があったはずだ。それを知る手がかりとしては、当時の日本人が書き残したものを読むことがあげられる。
それを収集した出版物としては、数年前に集英社から刊行された『戦争と文学』シリーズがある。同社は50年以上前にも『昭和戦争文学全集』を出しており、両シリーズとも太平洋戦争開戦時の日本人の様子を描いた作品が収録されている。どれも米英連合国に正面から挑んだことへの興奮と緊張があふれている。それまでの中国大陸での戦いでは後ろめたい気持ちを抱いていた人も、対米英では全く意識が変わったことが読み取れる。経済封鎖に苦しめられ、ギリギリまで追いつめられた日本が、やむにやまれず起こした戦争という位置づけだ。
太宰治が主婦を主人公にして開戦の日をユーモラスに描いた『十二月八日』ではラジオの開戦ニュースに「じっと聞いているうちに、私の人間は変わってしまった。強い光線を受けて、からだが透明になるような感じ。あるいは聖霊の息吹きを受けて、つめたい花びらをいちまい胸の中に宿したような気持ち」と反応し、さらに「目色、毛色が違うという事がこれほどまでに敵愾心を起こさせるものか。滅茶苦茶に、ぶん殴りたい。支那を相手の時とは、まるで気持ちが違うのだ」とストレートに表現している。
伊藤整は英文学と仏文学を学び、戦後は『チャタレイ夫人の恋人』の訳者としても知られるが、『十二月八日の記録』では「この日、我が海軍航空隊が大挙ハワイに決死的空襲を行ったというニュースを耳にすると同時に、私は急激な感動の中で、妙に静かに、ああこれでいい、これで大丈夫だ、もう決まったのだ、と安堵の念の湧くのをも覚えた」と記している。
詩歌となるともっとオクターブが上がる。ほとんどの詩人、歌人、そして俳人までが競い合って戦争を感動的に伝えている。それまで小説の陰に置かれた詩歌の作り手たちが表舞台に出てきた感じだ。三好達治には題も勇ましい『アメリカ太平洋艦隊は全滅せり』という詩がある。「ああその恫喝 ああその示威 ああその経済封鎖 ああそのABCD(注・米英中蘭のこと)線 笑うべし 脂肪過多デモクラシー大統領が 飴よりもなお甘かりけん 昨夜の魂胆のことごとくは アメリカ太平洋艦隊は全滅せり!(以下略)」
三好達治がこんな激しい調子の詩を作ったことは意外だが、それはアララギ派の歌人、斎藤茂吉についても言える。「何なれや心おごれる老大の耄碌(もうろく)国を撃ちてしやまん」
東日本大震災後に日本国籍を取得して移住した日本文学研究者、ドナルド・キーン氏は著書『日本人の戦争』(2009年 文藝春秋刊)で太平洋戦争時に書かれた作家の日記を調べ、当時の日本人の考えや生き方を探った。驚いたのは伊藤整や外国生活経験のある吉田健一のように欧米の知識を身につけた人が時流に加担していったことだという。伊藤整は先に引用した文章でも戦争を喜んでいるが、なんとヒットラーを称えるまでになる。
このような作家とは一味違ったのが永井荷風だという。自分の生活が戦争によって厳しくなるが、それを米英のせいにするのではなく、軍部のせいだと批判した。彼の日記『断腸亭日乗』の開戦日の部分では「日米開戦の号外出づ」という記述にとどめている。4日後の12日は、町のいたる所に掲示されている戦意高揚広告の文章のまずさを「駄句駄字」と切り捨て、『濹東綺譚』の舞台、玉ノ井に行ったと書いている。当時、彼が最も心配したのは、日本の未来ではなく、自分の美食、つまり英国製の紅茶やフランスワインが入手できなくなることで、それを知ったキーン氏は救われる思いがしたという。
そして戦争に抵抗した稀有な文学者として仏文学の渡辺一夫をあげる。『渡辺一夫 敗戦日記』を読んだキーン氏は目を疑ったそうだ。「行けという所にどこにでも行く。しかし決してアメリカ人は殺さぬ。進んで捕虜になろう」と書いているが、当時「捕虜になる」と書いた日本人は他にいなかったのではないかという。戦争中は米軍の通訳として多数の日本人捕虜と接していたキーン氏ならではの感慨だろう。
山田 洋






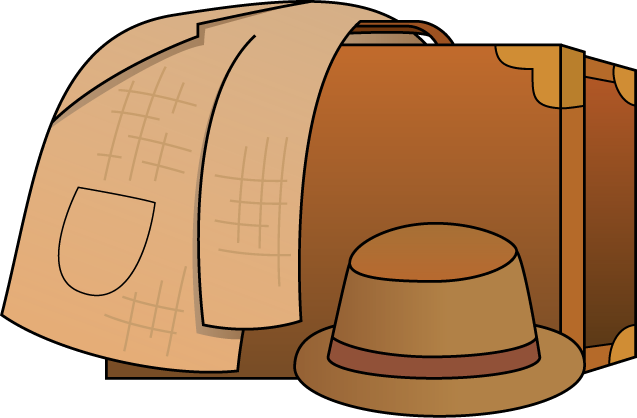
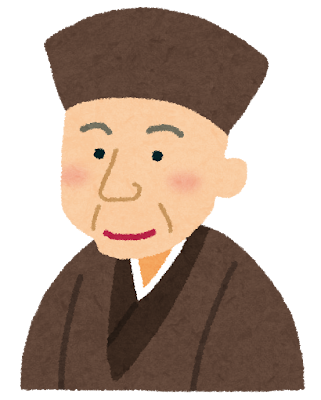

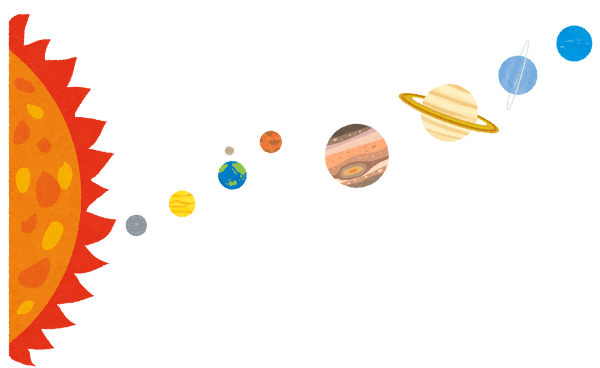







![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

