文芸広場
俳句・詩・小説・エッセイ等あなたの想いや作品をお寄せください。
今年もお盆がやってきた。
幼い頃からお盆は先祖が家に帰ってくる大切な日なのだと教えられて育った。
お盆は、先祖や亡くなった人達が苦しむことなく成仏してくれるようにと供養する期間だ。
現在では8月13日~16日の4日間を指すことが多いが、関東の一部では7月13日~16日の地域もある。
お盆の由来は、日本では推古天皇の606年に初めてお盆という行事が行なわれたと伝えられている。
お盆の行事は、迎え火にはじまり、送り火に終わる。
家の門や玄関で火を燃やし、その煙に乗って先祖の精霊が家に戻り、また帰っていく。
燃やした火を提灯につけ、先祖が迷わないようにと明りを灯す。
私が育った地域では、きゅうりとなすに割りばしで足を作り、とうもろこしのひげの尻尾をつけ、馬と牛をつくる。
祖父は、先祖がきゅうりの馬に乗ってきて、なすの牛に乗って帰るのだと言っていたことを最近よく思い出す。
馬で早くお迎えして、牛でゆっくり送るのだということを知ったのは、かなり大人になってからだ。
結婚してお墓参りに行くものの、お盆はただの休日に過ぎないと思っていた。
しかし、母を亡くし、この短い期間だけ家に母が帰って来ているような気がして、実家に帰らずにはいられない。
最近のニュースを見ていると、お盆はまるで海外旅行にいくためにあるのかと勘違いしてしまうほどだ。
日本古来の伝統行事にはひとつひとつ意味がある。
伝統行事を通じて、ゆとりや風情を感じるのもまた粋なものだ。
そしてまた、その意味を伝えていくのは私達の役目ではないだろうか。
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR

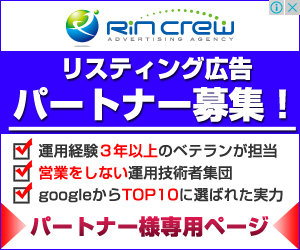




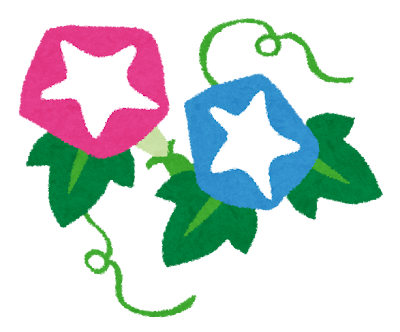




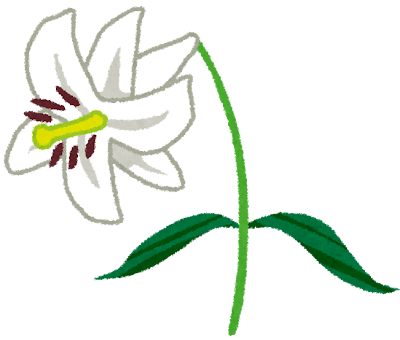

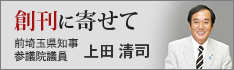
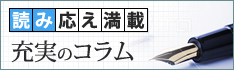

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

