トップページ ≫ コラム ≫ 男の珈琲タイム ≫ 孤丘とキツネ
コラム …男の珈琲タイム
「孤丘」という名に魅かれて、いつの間にか三年という歳月が流れていた。「孤」が「狐」と交差して私の眼球から脳裡へと焼きついてはなれないのだ。それはあたかもカクテルのように交わり合っている。さいたま市という、埼玉では一番の都会の片隅にその店はあった。否、もちろん今もある。小高いスロープの中程に高級感を漂よわせてその一軒屋が「孤丘」。そばの店だ。池波正太郎を気取るわけではないが、私は高級感より庶民的で小ぎれいな店が好きだ。だが、「孤丘」だけは例外なのだ。味も良い。接客もよい。もてなしの心を知っているのだ。それにも増してテーブルとテーブルの空間が広々としてすべて木の香でうずまっているのだ。男が独り、じっくりと思索にふける。そして思い出したように万年筆のインクを雑記帳にしみこませていく。
快感が走りぬけていく。そんな光景が現実となるような店なのだ。しかし、それは私だけのものかもしれない。私には「孤丘」と言う名がもう五十年近くも思い出のトランクの中にしまいこまれて決して忘れることができないでいたからだ。
孤の丘は私の人生観まで形成していたといっても過言ではない。もちろん、私は孤を狐とイメージしていた。東洋的風貌と思想を背骨として昭和の初期から中期にかけて名を馳せた詩人、蔵原伸二郎氏の詩にうら若い私は虜になっていた。「ずっと昔のこと、一匹の狐が河岸の粘土層を走っていった。それから何万年かたったあとにその粘土層が化石となって足跡が残った。その足跡を見ると、むかし狐が何を考えて走っていたかがわかる」蔵原氏の絶筆となった詩だ。私はなにかあるとこの詩を諳じては私の心の深渕にむかって語りかけていた。そして、私が蔵原伸二郎氏の絶筆前の詩に打たれたのは次の行だ。「・・・・・きつねはねむる。きつねはねむりながら光になり影になり、石になり雲になる夢を見ている……夢はしだいにふくらんでしまって無限大にひろがってしまって宇宙そのものになった。すなわち狐はもうどこにもそんざいしないのだ」
若かった私は蔵原伸二郎氏に心をうばわれた。私は生ある者の幽玄性と有限性を知らされた。人は必然的に出会い必然的に別れていく。だとすれば生を素直に甘受しよう。
そしてより積極的に人生に挑んでいこう。寂しさの極みを知って、極みの涯はもう喜びと希望以外ないと肝に銘じて生きてきたつもりでいる。
(鹿島修太)
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR




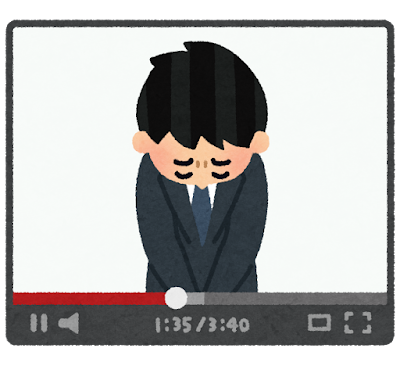


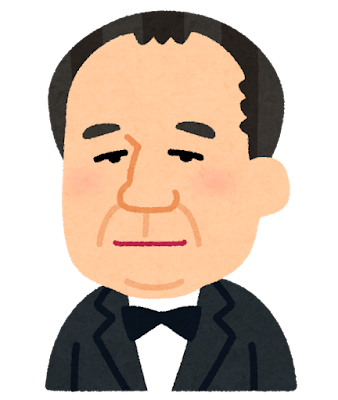








![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

