トップページ ≫ 教育クリエイター 秋田洋和論集 ≫ 高校に入る前に親がしてはいけない82のこと 第4章 高校入試のタブー(63)
教育クリエイター 秋田洋和論集
成績を見て“行ける高校”を選べば早いと思っている
昔も今も受験校選びの際に多くの人が悩むのは、
〝行きたい高校〟を選ぶのか、〝行ける高校〟を選ぶのか
の判断です。高校選びでは、調べれば調べるほど学校ごとの違いがハッキリしてくるので、「自分なりの判断基準」がしっかりしていないとすぐに情報の海でおぼれてしまいます。情報を整理しきれなくなって困り果てたときに出る言葉が、
「もう面倒だから、成績を見て〝行ける高校〟を探せばいいじゃない!」
なのです。
80年代までは、模擬試験の偏差値を元に、先生が「輪切り」して受験校を提示する、いわゆる「行ける高校を選ぶ」ことが一般的でした。90年代以降は中学校から偏差値が消えたために、先生の進路指導が変わってしまいました。「○○高校を受験したい!」という生徒の考えに対して「ちょっと無理じゃないか」「△△高校のほうが入りやすいぞ」といったアドバイスをしにくくなったからです。今の進路指導は、
・生徒の希望にストップはかけない
・高校の情報収集は、先生や中学校任せにせず、家庭でも積極的に
というように変わってきています。
皆さんは80年代までの受験システムと今のシステムでは、どちらを支持しますか?
私は今のシステムのほうが何倍もいいと思います。情報を集めることは家庭にとって負担になるかもしれませんが、
〝行きたい高校〟を早く見つけ、目標をしっかり見据えて日々の勉強に励む
ほうが、受験勉強の動機としては健全だと思うからです。
受験の結果がどう転ぶかは誰にもわかりませんが、直前期の「最後のひと踏ん張り」は、その後の人生において大きな経験となります。「行けるところを探せばいいや」という考え方では、「最後の力を振り絞る」気になるでしょうか。
親は高校受験を「合格・不合格」という結果だけで見てしまいがちですが、その過程にも大切なエッセンスはたくさん隠れているのです。
「高校に入る前に親がしてはいけない82のこと」(PHP文庫)秋田洋和より
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR

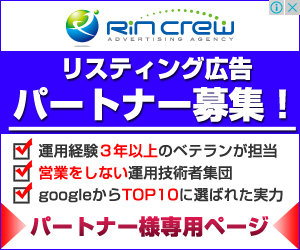

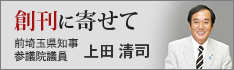
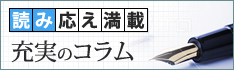

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](http://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

