トップページ ≫ 主筆のインク ≫ その後の「日本のいちばん長い日」
主筆のインク
昨日8月15日は70年目の終戦記念日ということもあって、昭和史に詳しい作家の半藤一利原作の映画「日本のいちばん長い日」を観にいった。戦争を終わらせるために本心を隠して苦労する鈴木貫太郎首相と阿南陸軍大臣を、それぞれ山崎努、役所広司が熱演し、ポツダム宣言受諾がいかに綱渡りのような状態だったか実感させてくれた。また昭和天皇を演じる本木雅弘は、国民や臣下への慈悲にあふれる姿そして陛下の戦争を終わらせる覚悟を、じつによく演じており、この映画をさらに印象深いものにしている。
劇中では陛下のご聖断をいただくまでのプロセスに加え、徹底抗戦を唱えて反乱を起こそうとする青年将校の姿も描かれている。この反乱が、クーデター未遂に終わった宮城事件である。この事件の中で青年将校たちは玉音盤を奪おうとしたり、放送局を占拠し徹底抗戦を訴えようとしたりする姿が描かれている。映画はこれで終わっているが、終戦後も徹底抗戦を訴える青年将校の反乱があったことを知っているだろうか。この埼玉県でも終戦から10日後の8月24日、国民に徹底抗戦を呼びかけようとする青年将校や予科士官学校の生徒らによって日本放送協会(現NHK)の川口放送所が占拠され、放送が9時間ストップするという事件が起こっている。この事件の舞台になった放送所の跡地がSKIPシティだ。
人は歴史から、そして失敗から何を学ぶかが一番大事だ。先の戦争で負けたの理由の一つに組織あって国がなかったということがある。陸軍と海軍は最後まで連携がとれず、特に陸軍は日本という国の存亡よりも、陸軍の組織そのものの存亡を優先させた。戦後、陸海軍は解体されたが、霞が関の役所にその伝統―つまり組織存続そのものが目的になっていまう―が残り、現在の肥大化した官僚組織につながっているのではないか。一方、その官僚組織をチェックする政治家も「市民・県民・国民のため」の前に自己の当選が目的化してしまってはいないか。そんなことを考えた70回目の終戦記念日だった。
小林 司
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR



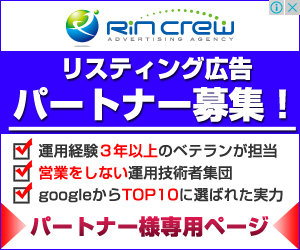






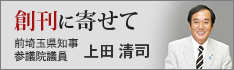
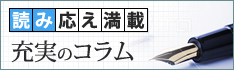

![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

