トップページ ≫ 社会 ≫ 街の戦災孤児の跡を追って ~後編
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
こんな暗黒の日々もすぐ転機が訪れる。上野駅近くに大きな青空市場ができたのだ。通称、闇市で、現在の「アメ横」がある場所だ。闇市はすごくにぎわい、浮浪児たちはここで下働きをするなどして生きる道を見出す。駅の構内で新聞売り、出口で靴みがきなどの商売を始める子もいた。タバコの吸い殻を拾い集め、燃えていない葉だけを出して、再び紙に巻いて売るシケモク売りというものもあった。女の浮浪児は1~2割といわれたが、靴みがきが多かった。何かがきっかけで売春をする子も少なからずいたようだ。その子たちの多くは大人の体になる前に売春に手を染めていたことになる。
上野の闇市の露店で商売していたのは主に在日朝鮮人だ。彼らの支配権が強まるのを危惧した警察は、テキ屋と呼ばれる日本人露天商を後押しして、朝鮮人の力を抑えようとした。さらにそこへヤクザも加わるようになると、浮浪児たちの中にはスリや万引きなど悪の道に進む者も出てきた。
1946年の春頃には上野の少年犯罪が多発するようになり、警察は治安対策に乗り出す。地下道に巣食う者をいっせいに捕まえ、子供は孤児院に送られる。しかし、職員の体罰がきついとか、食事がひどすぎるとかで、上野で食っていける自信のある子は脱走しようとした。東京湾にあった施設は四方を海で囲まれていたが、脱出を試みて溺死するという事件が発生した。
そんな殺伐とした状況下、中野区鷺宮で当時48歳の女性、石綿さたよが始めた私立の孤児院「愛児の家」の話には救いがある。終戦の年の秋、電車の中で一人途方に暮れていた垢だらけの少年を知人が連れてきたのがきっかけだった。少年は空襲のショックで記憶を失っていた。翌年1月から3人の娘たちに手伝わせて本格的に浮浪児を受け入れる。国の許可を得て委託費が支払われたが、微々たるもので、運営資金は自腹だった。
もともと裕福な家庭で、その貯蓄でまかなうつもりだったが、身を寄せた浮浪児姉弟に大金を持ち逃げされ、出鼻をくじかれる。それでもめげず、街頭募金や寄付を募ったり、家財を売ってしのいだ。だから子供たちに出す食事は決して十分なものではなかったが、石綿親子をはじめ多数の人々の善意が補った。最も多い時で107名いた子供たちは地元の小学校や中学校に通ったが、他所ではよく見られた施設の子への差別は少なかった。仲間の数が多かったことと、地元の人々が「愛児の家」を支えていたという事情があったからだ。
1948年1月には児童福祉法が施工された。子供全般の権利を守るためのもので、福祉の面からも支えることになった。孤児や施設に関しても定められ、孤児院は「養護施設」と改名された。しかし、子供たちが社会に出れば、元浮浪児に対する偏見が満ちていた。だから「愛児の家」では、できるだけ技能が身に付く職に就かせようとした。またキリスト教系の施設では、職業訓練をした子供たちを、世界に広がる支部を使って移民として送り出した。
こうして施設を巣立った子供たちも、著者の取材時にはほとんどが80歳に達していた。事業に成功して社会的地位を得た者もいるし、地道な職に就いて普通の人生を送った人は多い。反面、罪を犯して死刑になった者、自殺した者、ヤクザ組織から抜け出そうとしながら、ついに足を洗えなかった者など、違う軌道を歩んでしまった人もいる。
現在、児童養護施設に入所する子供の割合は年々増えている。入所の理由は家庭内暴力が多いという。石綿さたよを手伝ってきた三女の裕は、終戦後の浮浪児たちと現在の入居者の違いをこう指摘している。
「戦災孤児は空襲で両親が死ぬまでは家庭の愛情の中で生きてきた。それが失われても、友人や見知らぬ大人からでもいいから、子供時代に多くの愛情を受けてきた記憶があることが大切なんです。そういう経験があるからこそ、浮浪児だった子供でも社長になって社員に愛情を注ぎながら引っ張ることができたり、収入も乏しいのに結婚して努力に努力を積み重ねて子供をきちんと育て上げたりできたんです。けど、現在の虐待を受けた子供だと、大きくなってもなかなかそうはいきません。どっかで心が折れて、何もかも投げ出してしまったりするんです」(文中敬称略) (おわり)
バックナンバー
新着ニュース
特別企画PR




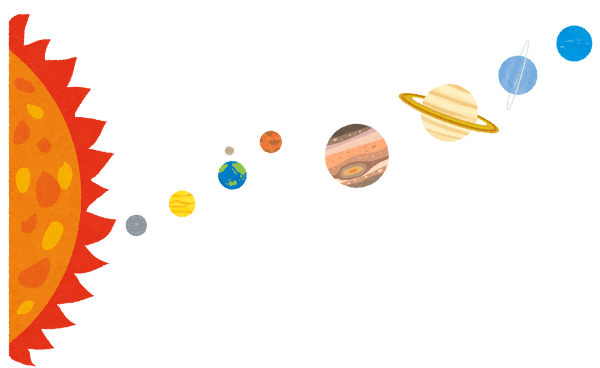




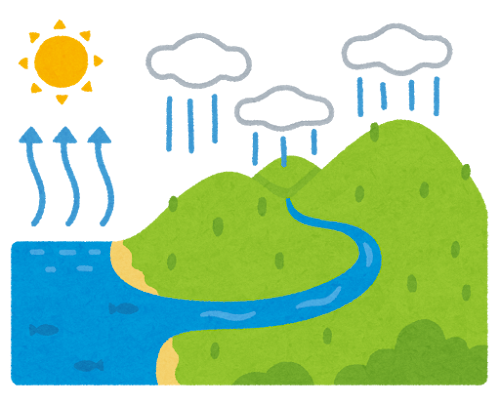
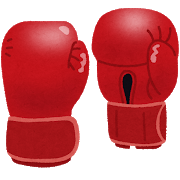






![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

