トップページ ≫ 社会 ≫ 官能小説の名手になった芥川賞作家
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
8月末に亡くなった宇能鴻一郎氏(享年90歳)はかつて週刊誌や夕刊紙から引っ張りだこの作家だった。「あたし、とっても感じるんです」といった調子の女性の独白で展開する官能小説が人気を集めたのだ。
彼は東京大学の大学院在学中の1961年に書いた『光りの飢え』が芥川賞候補作になり、次作の『鯨神』が半年後の第46回芥川賞を受賞した。巨鯨と人間の闘いを奔放な筆致で描き、前作からの成長度が評価されたようだ。受賞後は執筆に拍車をかけるとともに、ヨット、スキー、銃猟、海外旅行を楽しんでいた。
1971年からは徐々に官能小説に軸足を移し、翌年に女性独白体を書き始めた。少年時代からの官能への志向を、初めて一般向きの流露感のある形で表現できたという。これは画期的な発明と言えよう。文章は改行が多く、1行当たりの文字数も少ない。「あっ」とか「すごい」だけの行もある。具体的な性描写は抑えて、女性の語り口で読者の想像を搔き立てる。この手法なら、登場人物や場面の設定を変えるだけで話はいくらでも書けるはずだ。
官能小説の分野では彼より先行していたのが川上宗薫氏(故人)だった。この人は5回も芥川賞候補になって、高い評価を得ながらも受賞には至らなかった。悶々としていた時に講談社の文芸編集者から官能小説執筆を勧められ、1966年に中間小説誌「小説現代」に初登場してからは官能小説の第一人者として売れっ子作家になった。
この人の小説では性描写がリアルで、女性の体についても微細に書かれる。大量の注文をこなせたのは口述筆記という特技のお陰だ。口述した文章を速記者に書き取ってもらうのだ。稼いだお金で銀座のクラブに繰り出し、そこで口説いた女性との体験を小説の素材にした。苦渋の決断で官能小説を書き始めた結果、文壇の所得番付上位の常連になったことには、後々まで複雑な思いがあったようだ。
その点では宇能氏はすんなり方向転換したように見える。芥川賞決定の際の選考委員たちの選評の中の一つを紹介したい。宇能氏が才気豊かな作家であると認めつつも「作品のなかに彼の魂を投げ込んではいないように思われる。(中略)このおせっかいめいた忠告が宇能君によって理解されないようならば、マス・コミの攻勢に会って、彼はたちまち売文業者に転落して行くだろう」。
山田洋







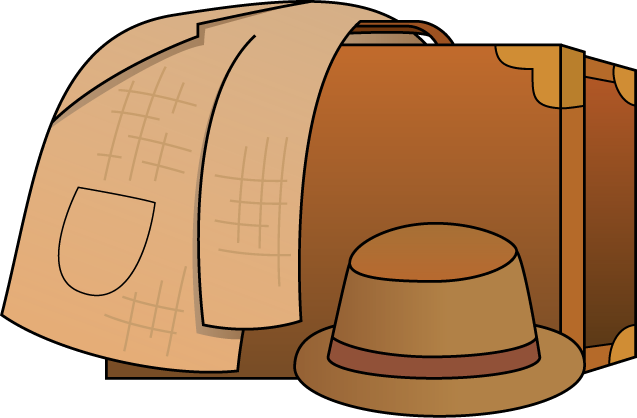
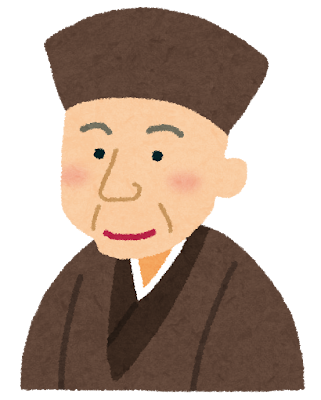

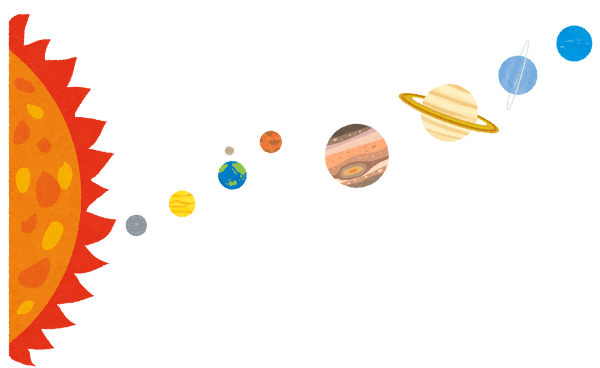






![FMふっかちゃん 88.5MHz[埼玉県深谷市のラジオ局]](https://www.qualitysaitama.com/wp-content/themes/201507/img/bnr/fm_fukka.png)

